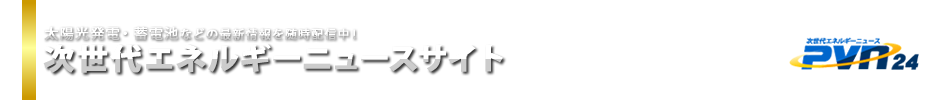産総研、効率よく電荷が流れる構造の有機薄膜太陽電池を実現
独立行政法人産業技術総合研究所は8日、JST課題達成型基礎研究の一環として行っていた有機薄膜太陽電池の開発において、結晶成長技術を駆使することで、九州した光エネルギーを効率よく電荷に変換し、効率よく電荷を取り出せる理想的な構造の発電層を構築することに成功したと発表した。
有機薄膜太陽電池は、製造工ストが非常に安く、形状や色といった設計の自由度が高いことから注目を集めている太陽電池だが、異なる材料をランダムに混ぜてバルクヘテロジャンクションと呼ばれる構造を構築するため、発電層の構造を制御することが難しく、発電効率の向上が大きな課題となっている。
今般の研究では、Ⅲ-Ⅴ族化合物太陽電池でよく使われる結晶成長手法を、バルクヘテロジャンクション構造の有機薄膜太陽電池の作製手法である共蒸着法に初めて適用し、その際に独自の工夫としてビフェニルビチオフェン呼ばれる材料をテンプレート(鋳型)層とし、その上にドナー材料(亜鉛フタロシアニン)とアクセプター材料(フラーレン)を共蒸着させることで、両材料の混ざり方や結晶性を制御することができ、電荷が効率よく流れる理想的なバルクヘテロジャンクション構造の構築に成功したという。今回開発した方法により効率の良い電荷生成、電荷取り出しが実現され、光電変換効率が1.85%から4.15%と、約2.2倍向上することを実証したと言えるだろう。
産総研は今後、この手法をさまざまな有機半導体材料に適用し、有機薄膜太陽電池のさらなる高効率化を実現させることで、フレキシブルで安価な太陽電池の実用化を加速していくことができるのではないかとしている。
独立行政法人産業技術総合研究所 – 研究成果
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2014/pr20140508/pr20140508.html