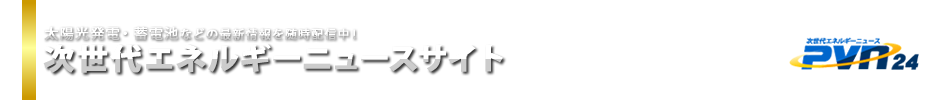ホタテの光で発電アップ…貝殻の反射をパネルに
自然エネルギーが注目を集める中、両面受光型太陽光発電パネルで、パネル裏面が受ける地面からの反射光を強めるのにホタテの貝殻を敷き詰めて発電効果を調べる実証試験が、北見市で始まった。
ホタテ産地で不要となった貝殻を活用し、日照時間も長い地元の特性を生かした取り組みだ。片面だけのパネルと比べ発電効率20%の増加を目標にしている。
実証試験に参加しているのは、パネルを製造するPVGソリューションズ(横浜市)、パネルの架台を作る伊藤組土建(札幌市)、コンサルタント会社のKITABA(同)、北見工大の4者で、今年10月から3年間、北見市で実験を行う。北見市も、試験の敷地(約450平方メートル)を提供するなどして協力している。
今回の試験で使うパネルは幅1メートル、長さ1・6メートル。計24枚使う。縦に3枚並べて、細長いパネルにし、すきまを空けて8列並べる。すきまは、通常の太陽光発電には設けないが、両面受光型のパネルでは、より多くの太陽光を地面に通し、裏面で光を受けるのに有効なほか、冬季には乱気流で回りの積雪を防ぐ効果もあるという。伊藤組土建の架台は、すきまを空けて設置できることから、試験に加わった。
試験では、細長いパネルの4列は地面に貝殻を敷き、残る4列は草地のままにする。それぞれは片面だけで3キロ・ワットの発電能力がある。積雪期は同じ条件となるが、雪のない季節に、裏面の反射光による上積み量の違いを計測する。2年目以降は、パネルの設置角度や、すきまの大きさ、敷き詰める貝殻の大きさなどを変えて、最適な条件を調べる。
両面受光型のパネルは、片面に比べて価格は高めだが、発電効率が上がることで、売電量の増加や狭い土地にも設置できる利点もあり、どれだけ効率が上げられるかが普及の鍵となる。
P社は2007年の設立で、両面受光型のパネルは昨年から量産を始めた。道の仲介で、太陽光発電に熱心な北見市を紹介され、研究や助言に欠かせないパートナーとして北見工大もあることなどから、同市で試験を行うことになった。
P社の担当者は「北見を実験場に選んだのはホタテの貝殻が容易に調達できること。鏡を使えば効率はいいかもしれないが、貝殻を利用すれば、環境にも優しく地域の特性も生かせる」と話している。
(記事:読売新聞)